「半夏生(はんげしょう)」ってなんか
風情のある言葉に聞こえませんか?
初めて聞いたときは、
夏の映画のタイトルか何かかな?と思いました。
いまさら聞けない「半夏生」について
ご紹介致します。
画像-http://yasounikki.exblog.jp/i20/
半夏生って何?
まず、「半夏生」とかいて
ハンゲショウと読みます。
半夏生は「雑節」(ざっせつ)という
季節の変わり目の一つです。
以前は、夏至の日から数えて
11日目にあたる日とされていましたが、
現在は、天球上の黄経100度の点を
太陽が通過する日となっていて
毎年7月2日頃になります。
この頃に降る雨は大雨になることが多く、
「半夏雨」(はんげあめ)や「半夏水」(はんげみず)と
言われています。
又、半夏(はんげ)の天候によって豊作になるか凶作になるかを占ったり、
麦の収穫祭を行うなど、農家にとって大切な日になります。
半夏生の日までに農作業を終え、この日から5日間
休みにする地方もあるそうです。
半夏生の名前の由来
どうして半夏生と呼ぶようになったのでしょうか?
実は、“半夏”とは「烏柄杓」(カラスビシャク)という
薬草の漢名になります。
烏柄杓が生える季節だから
「半夏生」と名付けられたと言われています。
ところが「半夏生」という植物もあるんです。
「半夏生」もこの頃に花をつける植物なり
このことが名前の由来となったとも言われています。
ややこしいですね。
スポンサーリンク
2つの半夏の花言葉
烏柄杓
画像-http://blogs.yahoo.co.jp/
別名 : 狐の蝋燭(きつねのろうそく)、蛇の枕(へびのまくら)
分布 : 日本全土、中国、朝鮮
科名 : ハンゲ
学名 : Pinellia ternate
花言葉 : 心落ち着けて
コルク層を除いた塊茎は、半夏(はんげ)という生薬で
半夏湯(はんげとう)、半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)などの
漢方方剤にも配合されています。
半夏生
画像-ja.wikipedia.org
別名 : 片白草(かたしろぐさ)、半化粧 (はんげしょう)
分布 : 本州から沖縄 海外では、朝鮮半島、中国、フィリピン
科名 : ドクダミ
学名 : Saururus chinensis
花言葉 : 内に秘めた情熱、内気
花が咲く頃、葉の表面が白色に変化していきます。
この為、片白草や半化粧とも呼ばれています。
スポンサーリンク
半夏生の頃
今年も半分が過ぎてしまいましたね。
歳をとるにつれて時間の経過がすごく早く感じませんか?
そしてこれからが夏本番!大分暑くなって来ましたね!
季節の変わり目でもあり、体調の崩れやすい時期です!
体に気を付つけて、後半も楽しく盛り上がりましょう!
半夏生と鯖の関係はコチラ。
半夏生とタコの関係はコチラ。









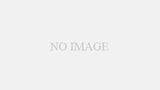
コメント