2018年の冬至は12月22日(土)です。
「冬至」って聞くと何を連想しますか?
よく聞くのが一年の間で昼が最も短く、夜が最も長くなる日。
そして柚子(ゆず)湯とかぼちゃ。さらには運気アップの日とされています。
ですがどうして、冬至の日にゆず湯とかぼちゃなんでしょうか?
今回は、冬至について少し深く探ってみました。
冬至とは?運気アップの日?
まず冬至についてなんですが、冬至とは北半球において
太陽の位置が1年で最も低くなる日です。
そして、日照時間が最も短くなり、
太陽の位置が1年で最も高くなる夏至と日照時間を比べると、
北海道の根室で約6時間半、東京で約4時間40分もの差があります。
2014年の冬至は、19年に一度の「朔旦冬至」(さくたんとうじ)でした。
「朔旦冬至」とは、新月(朔)と冬至が重なる日であり、
月の復活と太陽の復活が重なる日ということで、大変めでたいとされているんです。
そして、冬至は日が長くなる節目の日であることから
「開運」の日としても知られています。
年に一度のこの日にかぼちゃを食べてゆず湯に入って更に運気をあげましょう!!
夏至についてはコチラ
どうしてかぼちゃを食べるの?
その理由は冬至の日に「ん」のつく食べ物を食べると
「運」が呼び寄せられるためと伝えられています。
かぼちゃは、漢字で書くと「南瓜(なんきん)」とも言いますよね?
陰(北)から陽(南)へ向かうことを意味しています。
その他にも6種類あって、
「蓮根(れんこん)」「人参(にんじん)」
「銀杏(ぎんなん)」「金柑(きんかん)」
「寒天(かんてん)」「饂飩(うんどん)=うどん」があり、
合わせて「冬至の七種(ななくさ)」といわれています。
よく見ると、それぞれ「ん」を2つ含んでいることがわかると思います。
これは「運盛り」という縁起かつぎです。
そして運盛りの食べ物は栄養も豊富でそれを食べて寒い冬を乗り越えるといった
昔の先人たちの知恵でもあるんです。
これって土用の丑の日に「う」のつく食べ物、
うなぎを食べる感覚と同じなんですよね。
寒さが厳しい冬を乗り越える為に、
「運盛り」の栄養満点の食材を食べて今年の冬も乗り切りましょう!
スポンサーリンク
どうしてゆず湯に入るの?
柚子(ゆず)=「融通」がきく、冬至=「湯治」。
こうした語呂合せから柚子湯に入ると思われていますが、
もともとは運を呼びこむ前に厄払いするための禊(みそぎ)と言われています。
昔は、毎日入浴しませんでした。
そこで冬至に邪気を払って身を清めるのという意味で、
香りの強いゆずが選ばれたといいます。
又、ゆずは実るまでに長い年月がかかります。
ですので「苦労が実りますように」との願いも込められているようです。
試してみたいゆず湯の効果
ゆず湯には血行を促進して冷え性を緩和したり、
体を温めて風邪を予防したり、と言った効果があります。
更に、果皮に含まれるクエン酸やビタミンCによる美肌効果
そして疲労回復効果、ダイエット効果なんかもあるんです。
又、芳香によるリラックス効果もありますから、
元気に冬を越すためにも大いに役立つのです。
これは入るしかないでしょ?
ゆず湯ってどうやるるの?
ゆず湯の方法も各家庭によって違うようですが
代表的なものをご紹介します。
◆まるごと湯船に入れる
なるべく沢山入れたほうがいい香りがしていい感じです。
1・2個だとあまり香りを感じません。輪切りや半分にカットし、袋に入れてからお風呂へ。
ガーゼなどで袋を作り、中身が出ないようにします。
香りや成分も出やすくお掃除も楽。洗濯ネットでもいいですね。
皮膚が弱い人は、輪切りにしたゆずの果実を熱湯で
20 – 30分蒸らし、その後、布袋に入れて湯に浮かべるといいでしょう。
ゆず湯ってアレルギーは大丈夫?
肌の弱い強いに関係することで柑橘系のユズ、ミカンなどを
湯船に入れると肌の炎症を起こす人がいます。
というのも柑橘系のミカンの皮やオレンジ、ユズの皮には
リモネン成分が入っていて油を落とす効果があるんです。
それを人間の肌に付けることで
火傷のような症状を起こしてしまうんです。
数を減らすことで症状が出ないという方もおられますが、
ユズを入れたいときは十分に気をつけないと大変なことになります。
肌が弱い人は注意が必要です。
スポンサーリンク
芸能人だって動物だってゆず湯大好き!!
有名人だってゆず湯で疲れをとっていらっしゃるんです!!
いくつかご紹介します。
◆元美勇伝のメンバー三好絵梨香
冬至が近いので、一足先にゆず湯にしてみた
ゆずの香りで幸せ気分に心も身体も温まったよ

◆競馬評論家・花岡貴子
今日は冬至
柚子湯でしっかり温まりましょう

◆元モー娘。市井紗耶香
おつかれさまでした~☻
晩御飯はちゃんこ鍋に焼き魚に
しました満腹♬
家族みんなでゆっくりタイム。。
この時間が1番好き
こどもたちと将来何になりたいか~の話したり、
手遊びしたり…☻
パパさんタオとお風呂入ってくれたから女子3人でゆず湯にも入った^o^
あたたまった♡
◆渡辺美奈代
皆様
こんにちは
今朝は5時半起きで愛弥を部活の試合に送り出しサッカー
その後なづきは土曜授業で学校に登校学校
午後からはなづきも部活があるので野球
朝からず~と準備に追われている感じ・・・
私も午後から打ち合わせがあるので落ち着くことができません。(笑)
明日は冬至なので柚子湯の準備をしました。
子供達も冷え切った体で帰って来るので
柚子湯で温まってもらおうと思います。

◆国民的美魔女 草間淑江
今日は冬至!
ゆず湯にしました*(^o^)/*

◆元キャバ嬢で日本の作家、タレント、プロデューサーの立花胡桃
前回大失敗をしてしまったゆず湯温泉
子供に『つーちゃん、みかんがいい~※ゆず』とおねだりされて、
昨夜は再びゆず湯にチャレンジしてみました
前回の失敗を教訓に、ちゃんと百均で購入した洗濯ネットに入れて、
一ヶ所だけ切れ目を入れて浮かべたよ
子供が浴槽にオモチャを持ち込み過ぎて、見た目オモチャ湯なんですけど温泉
クジラやアヒル隊長を掻き分けて端っこに浸からせて貰いました
やっぱりゆず湯っていいですね
アロマだ
◆カピバラ
「カピバラの露天風呂」及び「カピバラの温泉」は
商標登録もされている冬の風物詩なんです。
17年前から、「ゆず湯」をカピバラにも提供しているとのこと。
冬至から「元祖カピバラの露天風呂」が「ゆず湯」に変わります。
かぼちゃを食べて、ゆず湯に入って今年の冬も元気に楽しみましょう!!







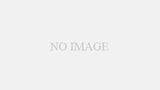
コメント